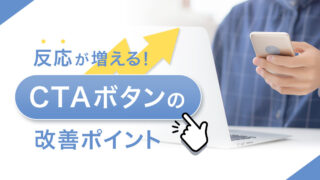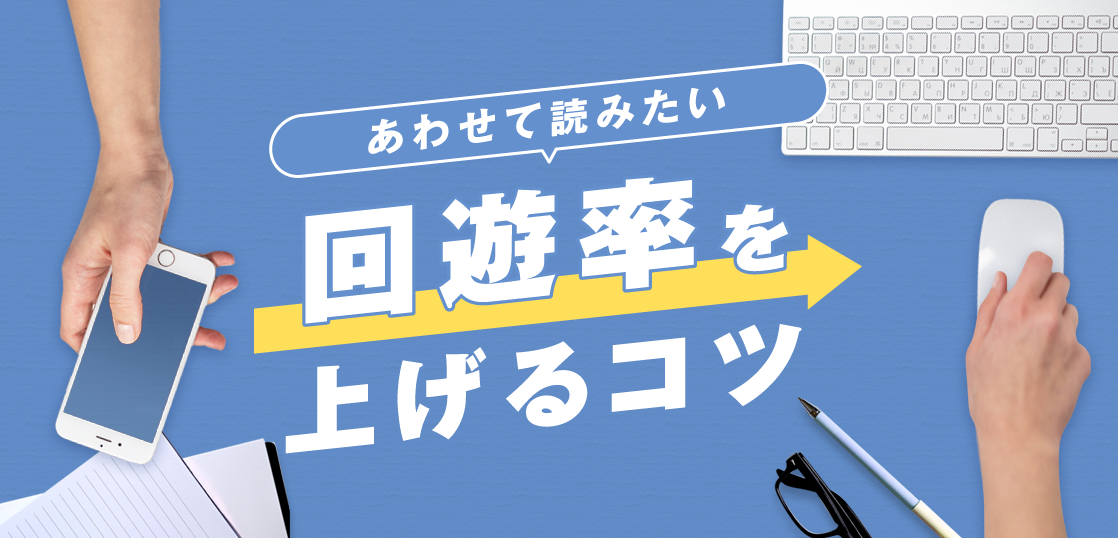「とりあえず、いかがでしたかを入れておけばいい。」記事最後のまとめ部分、そんな風に思っていませんか?
まとめ部分は記事全体のおさらいであり、読者に行動を促す大事な部分です。きちんと書けば回遊率アップや売上アップにつながります。
そこで今回は現役ライターが、記事最後のまとめの書き方を1行ごとに紹介します。読者に次のアクションを取ってもらうために、ぜひチェックしてくださいね。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
まとめの役割をおさらい
記事のまとめ文とは、記事の最後に、その記事の内容をカンタンにまとめた文章を指します。
本文を書いた後「まとめるの、面倒だな」と思っているかもしれません。しかし、まとめ部分の役割を知れば、気を抜くことはできないはずです。
まずは、記事のまとめの役割をおさらいしましょう。
- 情報を整理するため
- 次のアクションを迷わせないため
- ページの滞在時間を増やすため
情報を整理するため
アクセスしてくれた人が記事をしっかり読むとは限りません。あなたも、この記事を一語一句読んでいないと思います。
本文を読まずに、いきなりまとめに飛ぶ人もいるでしょう。そういう人のために情報を整理してあげましょう。「この記事はこういう内容なんだ」と分かるように説明するのです。
まとめで新しい情報は出さないようにしましょう。まとめは「その記事の要約」です。読者としては、本文で触れられていない主張が出てくると混乱してしまいます。
次のアクションを迷わせないため
記事を読んでいる人は「キーワードで検索するほど興味がある」状態です。例えば「WordPress テーマ おすすめ」で調べている人は、WordPressテーマを選びたいけれど判断材料がない人です。
つまり、次に何をするかを決めたいのです。まとめ部分があると、記事の内容をカンタンに理解できるため検討しやすくなります。
例えば商品紹介ページなら「買おう」と判断したとき、注文ボタンがあればスムーズに購入できますよね。背中を後押ししてあげることが、まとめの重要な役割と言えます。
ページの滞在時間を増やすため
先述した通り、記事は全文しっかり読まれる確率は低いです。まとめだけサクッと読んでページを閉じる人もいます。
しかし、まとめで気になる情報を見つけたらどうでしょうか?記事冒頭にスクロールして、最初から読み始めるかもしれません。
ページ滞在時間(エンゲージメント時間)が延びれば、Googleからの評価が高まり、その分上位表示されやすくなります。SEO対策の観点からも、まとめ部分はとても重要なのです。
まとめ部分の書き方
まとめ部分では、250~400文字程度で記事の内容を振り返りましょう。1行ごとのポイントはこちら。
- 1行目:何が書かれていたかを簡潔にまとめる
- 2〜3行目:大事なポイントを振り返る
- 4行目:読者に寄り添う
- 5行目:次のアクションを促す
詳しく見ていきましょう。
1行目:何が書かれていたかを簡潔にまとめる
まとめ1行目は「この記事に何が書かれていたか」を簡潔に伝えます。
- 今回は〇〇を紹介しました。
- 〇〇という人のために、〇〇についてまとめました。
- 今さら聞けない〇〇を解説しました。
つい「いかがでしたか?」を書きたくなりますが、実はあまり良い印象を与えないので使わないほうがいいです。
実際、予測変換(サジェスト)では「いかがでしたか むかつく」「いかがでしたか ゴミ」などネガティブなワードが出てきます…。せっかく最後まで読んでくれた人を、この一言で離脱させたくないですよね。
2〜3行目:大事なポイントを振り返る
まとめ2〜3行目では大事なポイントを振り返ります。ユーザーが検索したキーワードに対して、答えを伝えます。箇条書きにするのもよいでしょう。
まとめは復習の場所ですが、中には本文を読まずにまとめを最初に読む人もいます。パッと見て「何が大事なのか」が分かるようになっているといいですね。
文章がまとまらないなら、見出しをそのまま載せてしまうのもアリです。
4行目:読者に寄り添う
まとめ5行目は読者に寄り添ってください。例えば、ターゲットが「ブログ記事の書き方が分からない」と悩んでいる人だとします。
- 私も記事の書き方に悩んでいました。
- 時間がなくて、つい放置してしまうんですよね。
- せっかく書いているのに伝わらないなんて悲しいですよね。
あなたの率直な感想を書くのもひとつの手です。考えや意見を取り入れて、オリジナリティを出すのもGOOD!
「俺(私)のことを分かってくれる」と共感を呼べれば、次のアクションにもつながりやすくなります。
5行目:次のアクションを促す
まとめ5行目(最終行)は「次に何をするべきか」を伝えます。記事を読んでいる人は何か行動がしたくて、文章を読んでいます。「こうしたほうがいいですよ」と背中を押してあげましょう。
- このポイントを押さえて、○○してみてください。
- ○○に取り組んで、○○していきましょう!
- この記事を見ながら練習するのがおすすめです。
- すぐに見返せるよう、この記事をお気に入り登録(ビックマーク)しておきましょう。
記事で解決しなかったことや補足したいことがあるなら関連記事も紹介すると親切ですね。
- 以下の記事をぜひチェックしてください。
- こちらの記事もあわせて読んでみてください。
- ○○を詳しく知りたいなら、こちらの記事もおすすめです。
記事と関連するサービスを展開しているなら、以下のCTAも有効です。
- 問い合わせ
- 購入
- 申し込み
- 登録手続き
- ホワイトペーパーのダウンロード
読者が「で、結局何すればいいの?」と困ってしまわないよう、記事最後の文で次のアクションを教えましょう。
まとめのよくある質問
- Qまとめは何文字で書くといいですか?
- Q見出し名は「まとめ」がいいですか?
- Qまとめ(要約)が難しいです。どうすればいいですか?
まとめ
今回は記事最後の「まとめ」の書き方を紹介しました。
- 1行目:何が書かれていたかを簡潔にまとめる
- 2〜3行目:大事なポイントを振り返る
- 4行目:読者に寄り添う
- 5行目:次のアクションを促す
「滞在時間は長いから、最後まで読んでもらっているはず…なのに回遊率が低い。」もしかしたら、まとめの文章がうまく書けていないからかもしれません。
この記事を参考にすれば1行ごとに何を書けばいいか分かるので、時短にもなりますし、成果にもつながりますよ。
ユーザーを離脱させないためには関連記事がとても重要です。こちらの記事もあわせて読んでみてくださいね。