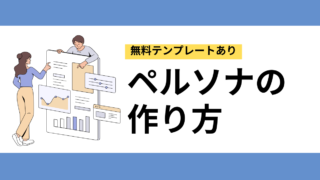サイトや記事の文体を決めるのは難しく感じますよね。でも面倒だからと言って後回しにするのはもったいないですよ。
文章のトーン&マナーを整えることで、会社の個性がしっかり伝わるんです。最終的にはお客様との良い関係が築けて、売上にもつながります。
この記事では「トーン&マナー」の作り方をわかりやすくお伝えします。ぜひ最後まで読んで、あなたの会社ならではの文体を作り上げてください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
文章の「トーン&マナー」とは?
「トーン&マナー(トンマナ)」とは通常デザインの表現ルールを指しますが、文章の表現ルールとしても使われるようになってきました。簡単に言うと、「文章スタイル」「文体」のようなものです。
文章は思った以上に、あなたの性格・会社の雰囲気が出ます。例えば、フレンドリーな言葉遣いで書くと、親しみやすい印象を与えます。逆にきちんとした言葉遣いだと信頼感を持ってもらえます。
- カジュアル:サイト全体のトーン&マナーを統一すると、読み手に自社の個性が伝わり、記憶に残りやすくなりますよ!
- 丁寧:サイト全体のトーン&マナーを統一することで、読者に貴社の個性が伝わり、記憶に残りやすくなります。
トンマナによってあなたの会社のイメージが決まり、読者が「この会社(この人)とは相性が良さそうだ」と判断する基準にもなるのです。
トンマナの作り方(3ステップ)
「トンマナを作る」って聞くと少し難しそうですよね。でも、自社の個性や魅力を伝えるためには、とても大切なステップなんです。以下の流れに沿って、一歩ずつ進めてみましょう。
- ペルソナを設定する
- コンセプトを設定する
- ユーザーが使う言葉を選ぶ
ペルソナを設定する
最初に、あなたのお客様はどんな人かをイメージしてみてください。
- 年齢
- 性別
- 職業
- 趣味、興味
- 1ヶ月で自由に使える金額
- 幸せを感じる瞬間
例えば、30代のビジネスマンなら、専門的な内容でもわかりやすく伝えるスマートな文体が適しているかもしれません。ペルソナを明確にすることで、どんな言葉が響くかが見えてきます。
こちらの記事ではペルソナの設定について詳しく説明しています。まだペルソナを作っていない方はぜひチェックしてくださいね。
コンセプトを設定する
次に、自社のどんな点を強調したいかコンセプトを決めましょう。「安全性を重視する」「革新的な技術を提供する」など、自社の特色を活かしたコンセプトが必要です。
会社や商品、サービスを1人の人格にするイメージで設定すると分かりやすいです。このコンセプトに合わせて使う言葉や表現を選ぶと、一貫性のあるトーン&マナーが生まれます。
ユーザーが使う言葉を選ぶ
最後に、実際のお客様が使っている言葉に耳を傾けましょう。SNSやフォーラム、レビューサイトなどで、ターゲット層がどんな言葉を使っているかをリサーチします。
若年層向けなら、流行語・若者言葉を取り入れることで距離を縮められます。逆に年配のお客様には、落ち着いた語彙と尊敬語を用いると良いでしょう。
最低限決めておきたいトンマナ
文章におけるトンマナは「一貫性を保つためのルール」です。内製でも外注でも、「この言葉はこの表現で」といったルールを決めておかないとバラバラになってしまいます。
例えば一人称では、「ぼく」「オレ」「私」それぞれ印象が変わりますよね。同じサイトの中で記事によって使う言葉が異なると統一感がなくなり、違和感を覚えてしまいます。
文章のトーンを定めるために、以下のようなポイントを最低限決めておくと良いでしょう。
- 文末表現
- 自分(自社)を表す言葉
- カジュアルさ
- ひらがなと漢字の使い分け
- 専門用語
- 記号の使用
- 避ける表現
文末表現
文章の印象を左右するのが、文末表現です。「です・ます」で書くか、「だ・である」で書くか、与えたい印象によって向いている文末表現が変わります。
- 敬体:私たちはお客様の満足を最優先に考えております。
- 常体:当社はお客様の満足を最優先に考えている。
「親しみやすい」「丁寧」といった印象を与えたいなら「です・ます調(敬体)」、「説得力のある」「簡潔」といった印象を与えたいなら「だ・である調(常体)」がよいでしょう。
迷うなら、とりあえず「です・ます調」にしておくのがベターです。
自分(自社)を表す言葉
自分(自社)を表す言葉はいくつもあり、それぞれに印象が異なります。
- ぼく
- 僕
- オレ
- 俺
- 私
- わたくし
- 小生
- 当方
- 自分
例えば、上品さを強調したい場合は「わたくしはお客様との関係を大切にしています」という表現が良いでしょう。「当方はお客様との関係を重視しています」という言い回しは少し固め、法人をターゲットにしている印象ですね。
カジュアルさ
カジュアルな表現を良しとしますか?
若い世代の消費者をターゲットにした商品のブログなら「この商品、使ってみたいですよね!」「○○じゃないですか?」「○○なんです!」といった砕けた表現も受け入れられるでしょう。
しかし、法人向けのサービス紹介では「当サービスは、お客様のビジネスをサポートします」というように控えめな表現が適しています。商品や会社のブランディングに合わせて、テイストを選ぶといいですね。
ひらがなと漢字の使い分け
ひらがなと漢字の使い分けも意識しましょう。ひらがなと漢字どちらで書くべきか、迷う言葉がありますよね。
| 漢字 | ひらがな |
|---|---|
| 〜する事 | 〜すること |
| 出来る | できる |
| 御座います | ございます |
同じ言葉でも、表記によって印象が変わってしまいます。特に複数人が書く場合、それぞれのクセが出てしまいバラバラになりがちです。
あらかじめルールを作っておくことで修正する必要がなくなり、確認作業の効率もアップするでしょう。
専門用語
専門用語は許可しますか?使うとしたらどんな用語でしょうか?
例えばIT企業向けブログでは「インターフェース」や「ユーザビリティ」などを使っても、読者は理解してくれるでしょう。ただ、一般消費者向けの記事では「使いやすさ」や「見た目」などに言い換えたほうが適切です。
避ける表現
炎上は避けたいですよね。あらかじめ「書かない内容」「使うべきではない表現」を決めておくと、トラブルを回避できます。過度な誇張や不適切な比喩も避けましょう。
例えば、これは文章ではありませんが、吉野家の元常務の発言が問題となりました。「生娘をシャブ漬け戦略」…あまりにもひどいですよね。
ネット社会では、不適切な発言はあっという間に炎上する恐れがあります。「何をどう書くか?」と同じように、「何を書かないか?」も考えておきましょう。
こんなに印象が違う!トンマナ事例
トンマナの参考として、3つのサイト・サービスを紹介します。それぞれペルソナや言葉選びが異なり、印象が変わることを確認してみましょう。
親しみやすい「Slack」
「Slack」というビジネスチャットサービスは、コミュニケーションを円滑にし、楽しくすることを目指しています。そのため、文章はフランクで親しみやすい雰囲気を心がけています。
たとえば、アイデア出しに関する記事での締めくくりを見てみましょう。
ぜひ、本記事を参考に、次なる事業展開を生み出すためのアイデア出しに取り組んでみてはいかがでしょうか。
効率良くアイデアを出したい!おすすめの方法とビジネスツールを紹介 | Slack
親しみやすく、Slackが提供する価値を自然と感じますよね。ほかにも、スマホアプリのアップデート文も”らしさ”が表れています。
Slackのブランドガイドラインでは、トンマナについてこのように書かれています。
We are humans, speaking to humans.
メディアキット | Slack
(私たちは人間であり、人間に向かって話しているのです。)
まるで友人に話しかけるような文章は、Slackの魅力です。
説得力がある「バズ部」
「バズ部」はコンテンツマーケティングを学習できるメディアです。サイトは一貫して「で・ある調」を使用し、説得力を高める文体を採用しています。
例えばこの文章を読んでみてください。
「最初に理解さえしていればうまくいっていただろうに…」と思うケースをこれ以上増やしたくないので、この記事でコンテンツマーケティングとSEOの違いを明らかにする。ぜひ理解して成果につなげてほしい。
コンテンツマーケティングとSEOを混同している企業は成果が出ない
「きちんと学べば読者も成功できる!」という確信のようなものが感じ取れますよね。直接的で力強い文体は信頼感・期待感を強化できるのです。
トンマナが徹底されている「note」
「note」はクリエイター向けのプラットフォームです。note編集部の記事は、親しみやすさを重視した文体で書かれており、幅広い読者にアプローチしています。
でも、創作に慣れていなくて、何をどうやって表現したらいいのかわからず、一歩踏み出せない人もいるかもしれませんね。ここでは、これからnoteを使ってみたいけれど、何か取っかかりがほしいな、という人に向けて、創作のヒントを紹介していきます。
noteで書くテーマに迷ったときの3つのアイデア|note編集部|note
読者に寄り添うような言葉遣いや表現が使われ、情報を提供するだけでなく、読者とのコミュニケーションを大切にしていることが感じられますね。
なお、noteはトンマナを「トーンオブボイス」として明確にし、社員に共有しているようです。
もともとnoteは「noteさん」という人格を2年ぐらい前に作っており、もともと事前にシステムを作る前からそういう話は動いてました。これを具体的に使えるようにしておくのが、トーンオブボイスの取り組みの1つです。
「noteらしさ」を共通言語化。noteが作る、全員参加型のデザインシステム | キャリアハック
記事・サービスを通して「どんな印象を持って欲しいか」を徹底しているのが分かります。
まとめ
この記事では「自分らしさ」を伝える文章のトーン&マナーの作り方について紹介しました。トンマナは、読者に対して自社の個性を明確に伝え、ブランドイメージを強化する上で不可欠です。
- ペルソナを設定する
- コンセプトを設定する
- ユーザーが使う言葉を選ぶ
この記事を参考に、貴社のホームページにもトンマナを取り入れて、顧客とのつながりを深めてくださいね。