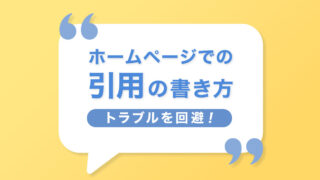ホームページ運営に関連する法律はいくつも存在します。知らず知らずのうちに違反し、大きなトラブルに発展するかもしれません。
この記事ではWEB担当者・経営者が知っておきたい法律に焦点を当て、どんな行為が対象となるかを説明します。違反した場合の影響や遵守するための対策も合わせて載せているので、ぜひチェックしてみてください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
知っているようで知らない「著作権法」
ホームページ上にはテキスト・画像・動画などを掲載しますよね。自社で制作したコンテンツなら問題ないのですが、他者が作成したコンテンツには注意が必要です。
無断で使用する行為は著作権侵害にあたり、損害賠償請求や法的措置を受けるリスクがあります。
コンテンツの無断利用はNG
著作権とは「著作物」を創作した著作者に与えられる権利を指します。
- 文章
- 写真
- 動画
- 音楽
- イラスト
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法 | e-Gov法令検索
例えば「他社サイトの文章をコピペして、自社のサイトに載せる」、これは明らかに無断転載(無断複製)ですね。
特に気をつけたいのが、安いライターに依頼する時です。オリジナル記事の制作を頼んだはずなのに、ライターがコピペ記事を納品したとします。その場で気づければいいのですが、記事を公開してから外部に指摘されたらどうでしょう。…困るのは会社ですよね。
違反すると罰金1,000万円
著作者からの許可を受けずに勝手に利用した場合、損害賠償請求がなされる可能性があります。賠償金額は侵害の程度や影響によって大きく異なります。
また、違反の内容によりますが、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人に対しては3億円以下)の罰金という大きなペナルティを受けます。(第百十九条、第百二十四条)
対策:許可を得る・引用する
著作権法の目的は著作者の権利を守ることです。
著作物を利用したい時は、著作者の許可を得る(使用料を支払う)のがベストです。ただ、毎回 契約書や承諾書を交わすのは現実的ではありませんね。
そこで、条件を満たしたら許可を得ずとも使える、という特別ルールが「引用」です。どうしても他人のコンテンツを載せたいなら、引用をうまく使ってください。
間違えるほど似せてはダメ「不正競争防止法」
不正競争防止法は、事業者間の健全な競争を促し、消費者の利益を守るために制定された法律です。カンタンに言えば「他社の商品やサービスを模倣してはいけないですよ」という内容です。
「サイトのデザインや文章を考えるのが面倒」「有名企業をマネすれば売上が増えるんじゃないか」と思うかもしれません。参考にするのはよいのですが、そっくりのホームページを作るのはアウトです。
商品名やロゴの丸パクリはNG
サイト制作において、競合他社のサイトからインスピレーションを得るのは一般的です。しかし、商品名やロゴ・ドメインなどをそのまま使うと「周知表示混同惹起為(じゃっき)行為」にあたります。
消費者があなたのサイトと競合他社のサイトを混同するほど似たものを作り出してはいけない、ということです。
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
違反すると罰金500万円
不正競争防止法に違反した場合、民事上では差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などがなされます。
刑事上では、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課されることがあります。法人に対しては代表者・代理人が罰せられる上に、最大10億円以下の罰金が科される可能性も…。違反が発覚した場合のダメージは計り知れませんね。
対策:オリジナリティを出す
オリジナリティ(独自性)はビジネス成功の鍵です。競合と差別化するために、自社ならではの強みを明確に打ち出しましょう。
訪問者に強い印象を残し、自社を選んでもらえるようなサイトを作ってください。他社にはないベネフィットを見つけたいなら、こちらの記事がおすすめです。
医薬品・化粧品・健康食品の表現を規制「薬機法」
「薬機法」の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。医薬品や医療機器・化粧品・健康食品を扱う場合は注意してください。
ざっくり言うと、誤解を招くような効果や効能をうたうことが厳しく規制されています。例えば「飲むだけで痩せる」といった過大な宣伝は、消費者を誤認させるとして違反対象となります。
効果・効能に要注意
薬機法では効果効能の表示に関して厳しいルールが設けられています。具体的には「シワが消える」「10歳若返る」といった表現は使用できません。
第十章 医薬品等の広告
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索
経営者やWEB担当者は、この点を慎重に考慮する必要があります。また、記事制作代行会社やアフィリエイターに依頼する際も、違反がないかチェックしましょう。
違反すると取引金額に応じた罰金
薬機法に違反した場合、行政指導が行われるほか罰金が科される可能性があります。
例えば広告規制違反(誇大広告)では、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくは両方)に処されることがあります。さらに、取引の金額に応じて、課徴金を納付するよう命じられたケースも…。
企業の信用を大きく損なうだけでなく、経営にも甚大な影響を及ぼすでしょう。
対策:ツールを使ってチェック
薬機法の知識を持つ人に記事を書いてもらうのがベターですが、そうでない場合は納品物のチェックを行いましょう。
1フレーズのみなら、無料でチェックできるツールがあります。
例えば「若返る」というフレーズはNGだと確認できます。文章全体をチェックしてほしいときはツールを月額契約するか、弁護士やコンサルタントに依頼しましょう。
実際より ”良く” 見せてはいけない「景品表示法」
「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」は、消費者が商品やサービスを適切に選択するための法律です。
(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov法令検索
実際よりも良く見せかけたり、安く見せかけたりするような、消費者を誤解させる可能性のある表現は禁止されています。
根拠のない「ナンバーワン」に要注意
根拠・事実がないのに「ウチの商品が一番です!」と書くと、景品表示法違反にあたります。例えばこのような表現は景品表示法違反にあたります。
- 地域No. 1(※第三者の調査など根拠がない)
- 世界初(※他社で類似商品が販売されている)
- 食事制限なしで−5kg(※裏付けとなる資料がない)
- 最安値(※他社の割引サービスを適用していない)
- たった〇〇円(※他にも追加費用がかかる)
特に「No. 1」は訴求力が高いので使いたい言葉ですし、他社サイトでもよく見かけますよね。しかし、主張を裏付ける客観的な根拠やデータがなければNGです。
違反すると罰金300万円
景品表示法に違反した場合、措置命令が下されることになります。表現の根拠となるデータを提出しなければいけません。措置命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
対策:嘘や誇張は言わない
ホームページ・サイトでは嘘や誇張は使わないようにしましょう。
例えば「地域No. 1」をうたいたい場合でも、裏付ける根拠がなければ使用してはいけません。代わりに、実績件数やお客様の声など事実に基づいた表現を選んでください。
また、誇張せずとも心理をうまく使えば読者の心をつかめます。当サイトでは文章で心をつかむためのヒントも公開していますので、あわせてチェックしてみてください。
連絡先などを明確に表示「特定商取引法」
特定商取引法は、通信販売を含む特定商取引に関して、消費者の保護を目的として設けられた法律です。
ホームページは、最終的に商品購入やサンプル注文などに誘導する形になっていると思います。つまりネットによる広告がきっかけで申し込みを行う取引=通信販売にあたります。
消費者庁運営の「特定商取引法ガイド」が分かりやすいので、確認しておくことをおすすめします。
連絡先は掲載していますか?
ネット上で商品やサービスを購入する際、消費者は不安を感じます。代表的なのは「商品は本当に届くのか?」「個人情報が悪用されないか?」という心配ですね。
万が一トラブルが発生したとき、事業者に連絡したいのに電話もつながらない、メールアドレスも存在しないみたい…となったら、消費者は泣き寝入りするしかありません。
特定商取引法はこのような不安を減らし、消費者が安心して取引できる環境を提供するために、事業者に対して情報公開を義務付けています。
違反すると罰金300万
特定商取引法を違反した場合、事業者は業務改善指示や業務停止命令の対象となる可能性があります。違反が公になれば、マスコミやSNSを通じてより多くの人に知られ、事業継続が困難になるかもしれません。
罰則については、違反の内容によって異なりますが、個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。法人の場合は3億円以下の罰金が科される場合があります。
対策:「特定商取引法に基づく表記」を作成する
特定商取引法に基づく表記は、事業者がホームページ上で表示しなければならない情報です。
1.広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
通信販売|特定商取引法ガイド
- 事業者の氏名(名称)
- 事業者の住所、電話番号
- 販売価格
- 送料、その他かかる費用
- 支払い時期、方法
- 商品の引き渡し時期
- キャンセル・返品・交換の方法
特定商取引法に基づく表記ページをヘッダーやフッターなどにリンクとして設置しましょう。消費者が簡単に確認できるようにするのです。
メルアドも対象「個人情報保護法」
個人情報保護法は、個人を特定できる情報、つまり個人情報の取り扱いに関して厳格な規制を設けています。個人情報には、氏名・生年月日・顔写真などが含まれます。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 顔写真
- メールアドレス
- ID、ユーザー名
特にサイト運営で注意したいのは、メールアドレスやユーザー名などのオンラインでの識別情報です。詳しく知りたい方は政府広報オンラインをチェックしてみてください。
メルマガやユーザー登録
メルマガ購読や会員制サイトでユーザー登録を行う際、メールアドレスやユーザー名の入力を求めますよね。意外と知られていませんが、こういった情報も個人情報に該当します。
例えばメールアドレスでもドメイン名などから特定の個人を識別できるからです。特に、メルマガや会員制サイトを利用している場合、個人情報保護法を知っておく必要があるでしょう。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索
違反すると罰金50万円
個人情報保護法に違反した場合、個人に対しては1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、法人(代表者・代理人など)に対しての罰金は最大1億円となりますので、十分注意してください。
対策:プライバシーポリシーを明記する
個人情報の取り扱いに関する方針をプライバシーポリシーとして明記し、公開しましょう。プライバシーポリシーには、以下のような内容を含めます。
- 利用目的
- 利用目的の範囲でのみ利用すること
- 情報漏洩などが起こらないよう安全に管理すること
- 第三者に提供する前に本人の同意を得ること
- 本人から開示が求められたら迅速に対応すること
- 個人情報取り扱いに関する相談先・連絡先
個人情報を適切に取り扱えるかどうかは、法律遵守だけでなく、ユーザーからの信頼獲得にも直結します。もしプライバシーポリシーページを作成していない場合は、今すぐに取り組みましょう。
メルマガ運用するなら「特定電子メール法」
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、迷惑メールを規制し、良好なインターネット環境を保つことを目的に制定された法律です。ホームページでメルマガを運用する際には、この法律を遵守する必要があります。
メルマガ解除を明記していますか?
特定電子メール法の対象となるのは、サイトへの誘導や商品の宣伝を目的としたメールです。
利用者がメルマガ登録を行ったものの、関連性のない商品の広告が送られてくると不快に感じるでしょう。メール内にメルマガ解約の方法や送信者の情報が記載されていないと、受信者は配信を停止できませんよね。
違反すると罰金100万円
特定電子メール法を違反した場合、総務大臣や内閣総理大臣から業務改善命令や停止命令が出されます。
また、個人に対しては1年以下の懲役や100万円以下、法人に対しては3,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十四条 三千万円以下の罰金刑
二 第三十三条、第三十五条又は前条 各本条の罰金刑
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索
対策:配信停止できるようにする
メルマガを配信する際には「オプトアウト」の仕組みを必ず設けてください。オプトアウトとは、受信者がメールを不要と判断した場合に、すぐに配信を停止できるようにする、ということです。
具体的には、メール内に以下のような情報を明記します。
- 送信者の氏名、名称
- 受信拒否できる旨
- 受信拒否をするためのメールアドレスまたはURL
- 送信者の住所
- 苦情・問い合わせなどを受け付ける電話番号、メールアドレス、URL
メルマガを運用する際には特定電子メール法に従い、受信者に迷惑をかけないようにしましょう。
まとめ
今回はホームページを運営する上で知っておきたい法律とその対処法を紹介しました。
- 不正競争防止法
- 薬機法
- 景品表示法
- 特定商取引法
- 個人情報保護法
- 特定電子メール法
「知らなかった…」という法律もあったのではないでしょうか。大きなトラブルに発展する前に、対応しておくことが大事ですよ。
2023年10月1日からは、ステマ規制(景品表示法)も始まりました。こちらも合わせて確認しておきましょう。