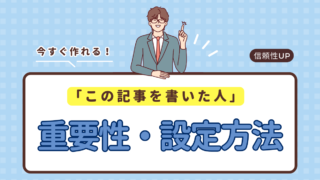生成AIを活用した記事作成は効率的ですが、事実とは異なる情報が含まれる場合があります。もしも検証せずに公開すると、企業の信用低下や読者の誤解を招いてしまうかもしれません。
そこで今回は、AI記事の品質を高めるための「ファクトチェック方法」を分かりやすく解説します。情報発信の信頼性を守りたい方は、ぜひ参考にしてください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
AI記事に欠かせない「ファクトチェック」
生成AIは高度な文章作成能力を備えていますが、事実とは異なる情報を出力する場合があります。
- 実在しない統計データや数値を提示する
- 誤った人物名や肩書を正確な情報のように記載する
- 存在しない企業や団体を実在するかのように紹介する
- 古い情報を最新情報として提示する
- 引用や出典を改変して提示する
- 複数の事実を混同して誤った結論を導く
- 翻訳の誤りにより内容や意味が変化してしまう
誤情報を企業が発信すれば、ブランドの信頼低下や取引先への損害につながる危険性が高まります。
記事の質と信頼を維持するためには、一次情報や公的な発表と照合し、裏付けを取ったうえで公開する体制が欠かせません。
ファクトチェック5つの原則
国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)は、検証作業で遵守すべき5つの原則を掲げています。
- 非党派性と公正性
- 情報源の基準と透明性
- 資金源と組織の透明性
- 検証方法の基準と透明性
- オープンで誠実な訂正
正確性と信頼性を担保するための指針と言えるもので、生成AIが作成した記事の検証にも応用できます。
非党派性と公正性
特定の立場や思想に偏らないことは、記事検証の大前提です。
AIによる記事も、検証者の主観で情報を取捨選択してしまえば、事実の歪曲につながります。例えば、同じデータでも片方の立場を強調すると、読者は誤解してしまうかもしれません。
情報源の基準と透明性
AIが生成した情報には、出典不明や一次情報に遡れないケースが少なくありません。
出典(発行元や著者名)を明示し、読者自身が情報を確認できるようにすることで、記事の信頼性は高まります。
資金源と組織の透明性
検証を行う組織や個人が、誰から資金を得ているのか、どのような構成で運営されているのかを明らかにすることも重要です。
資金提供者の意向が検証内容に影響する場合、信頼性が損なわれます。企業サイトの記事では、運営者情報や問い合わせ窓口を明確にし、情報発信の背景がわかるようにしておくべきです。
検証方法の基準と透明性
検証対象の選定基準から、取材やデータ収集、訂正までの流れを明確にすることで、読者はその検証が公正に行われたと判断できます。
AI記事の場合、生成プロンプトや参照した資料を記録し、第三者が検証可能な形にすることが理想です。また、読者から検証対象の情報提供を受け付ける体制も信頼性向上につながります。
オープンで誠実な訂正方針
誤りを発見した際は、訂正内容をわかりやすく公開し、読者の目に届くようにします。
特にWeb記事は公開後もアクセスされ続けるため、訂正履歴や更新日を明記することが大切です。
AI原稿をファクトチェックする方法
AIが生成した文章は便利ですが、事実の裏付けが取れていない場合があります。ここからは、実際にAI原稿の信頼性を確保するためのポイントを紹介します。
- プロンプトと出力を記録する
- 公的機関の情報と照合する
- 出典(一次情報)を確認する
- 固有名詞・数値を検証する
- 複数AI・人間のクロスチェック
- 情報源の信頼性・専門性の評価
- 情報の鮮度を確認する
- 文章に曖昧さ・誇張がないか確認
- 専門家レビュー・社内レビュー
- ファクトチェックツールを活用する
プロンプトと出力を記録する
生成AIの回答内容を検証するためには、質問文(プロンプト)と出力結果を全て保存しておきましょう。
履歴を残せば、後からどのような指示に基づいて文章が生成されたのかを正確に把握できます。
例えば、初回生成文と修正版を比較すれば、どの部分を訂正したのかが明確になり、誤りの発生原因を突き止められるでしょう。
日付や担当者名を含めて整理し、社内で共有できる形式で保管することが望ましいです。
公的機関の情報と照合する
AIが生成した文章の正確性を確保するためには、政府機関や自治体、国際機関、主要報道機関など、公的かつ信頼度の高い情報源との照合が欠かせません。
特に法律、制度、統計データに関する記述は一次情報に直接当たり、誤りや古い情報を排除する必要があります。
具体的には、経済統計であれば総務省統計局や世界銀行のデータ、医療情報であれば厚生労働省やWHOの発表を基準とするとよいでしょう。
以下の記事では信頼性の高い情報源(サイト)をまとめています。あわせてご参考ください。
出典(一次情報)を確認する
AIが出典を提示しても、それだけで安心してはいけません。
例えば存在しない引用や改変された情報を基に記事を作成すると、読者に誤解を与えるだけでなく、企業の信頼低下にもつながります。
論文や調査レポート、公式発表などの一次情報に直接アクセスし、内容が正確かどうかを精査しましょう。
固有名詞・数値を検証する
AIは、人名や地名、企業名、統計値などの情報について、誤った内容を提示する場合があります。
そのため、固有名詞や数値は必ず複数の信頼できる情報源で照合することが重要です。例えば人物名や肩書は、企業の公式サイトや公的な登録情報で裏付けを取るようにしましょう。
情報源の信頼性・専門性の評価
記事の正確性を確保するには、情報源が信頼できるかどうかを見極めることも欠かせません。著者の経歴や実績を確認し、専門家が発信している情報を優先的に採用しましょう。
例えば、医療分野であれば病院や診療所・薬局が信頼度の高い情報源となります。ただし、営利目的や特定の立場に偏った発信は、事実の選別や表現にバイアスが含まれる可能性があるため注意が必要です。
情報の鮮度を確認する
生成AIは過去のデータを学習して文章を作成するため、最新情報を反映できない場合があります。学習データが収集された時期以降に発生した出来事や制度改正は、出力内容に含まれないケースが多いのです。
そのため、情報の発行時期や時系列を意識して検証することが重要です。特にリアルタイム検索できるAIを使えば、時代遅れの記述や誤解を招く表現を避けられるでしょう。
文章に曖昧さ・誇張がないか確認
生成AIは、事実を補うために推測や曖昧な表現を用いることがあります。
「〜といわれている」や「〜かもしれない」といった言葉は、裏付けが不十分な場合に混入しやすく、読者に不確実な印象を与える要因となります。
また、根拠のない強調や断定も、誤解や過剰な期待を招く危険があります。例えば、統計的根拠がないのに「業界で最も優れている」と表現すれば、事実誤認につながるでしょう。
以下の記事では、サイトを運営するうえで知っておきたい法律をまとめています。「景品表示法」「薬機法」と聞いてピンと来ない方は、一度チェックしてみてください。
専門家レビュー・社内レビュー
高い専門性が求められる記事、特にYMYL(医療・法務・金融・安全)に該当する場合は、外部専門家による監修が不可欠です。
専門家は事実の正確性だけでなく、用語や表現の妥当性も確認できるため、誤情報や誤解を防げます。
また、社内レビューでは役割分担を明確にし、リサーチ担当、法務担当、編集者、最終責任者といった複数の視点でチェックを行うことが効果的です。
例えば、医療記事であれば、医師による監修後に編集部が読者目線での読みやすさを確認します。
多段階の検証体制によって、正確性と信頼性の両立が可能となり、読者に安心感を与えられるでしょう。
ファクトチェックツールを活用する
情報の真偽を効率的に確認するには、ファクトチェック専用サービスを活用するのもひとつの手です。
例えば、Googleが提供する「Fact Check Explorer」は、世界中の検証記事を横断的に検索でき、根拠や出典を素早く確認できます。
また、国際的な検証サイトであるSnopesやPolitiFactも、社会的関心の高いテーマや話題の情報について信頼できる検証結果を提供しています。
大量の記事やデータを扱う場合、手作業のみでは時間がかかるため、専用サービスを併用することで作業効率と精度を両立できるでしょう。
複数AIに質問する
AIが生成した回答を鵜吞みにするのは危険です。とはいえ、毎回レビューをするには時間や予算が足りないかと思います。
その場合は、複数の生成モデルで同じ質問をしてみてください。回答の一致点や相違点が明らかになり、誤情報を見抜きやすくなります。
普段ChatGPTを使っているなら、GeminiやClaude、perplexityなどに切り替えてみましょう。
まとめ
AIを活用すれば記事作成を時短できますが、誤情報を含むリスクを伴います。企業の信頼を守り、成果につなげるためには、公開前のファクトチェックが欠かせません。
- プロンプトと出力を記録する
- 公的機関の情報と照合する
- 出典(一次情報)を確認する
- 固有名詞・数値を検証する
- 複数AI・人間のクロスチェック
- 情報源の信頼性・専門性の評価
- 情報の鮮度を確認する
- 文章に曖昧さ・誇張がないか確認
- 専門家レビュー・社内レビュー
- ファクトチェックツールを活用する
しかし、リソース不足でチェックができなかったり、サービスや専門家への依頼は予算が回せなかったりと悩んでしまうケースもあるでしょう。
リンキープスは、AIで作った原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに整えるサービスを提供しています。
プロンプトテンプレートやGA4レポートもついて、毎月の発信がラクに・質高く続けられます。AIが生成した文章から集客できていない方は、ぜひ一度詳細をご覧ください。