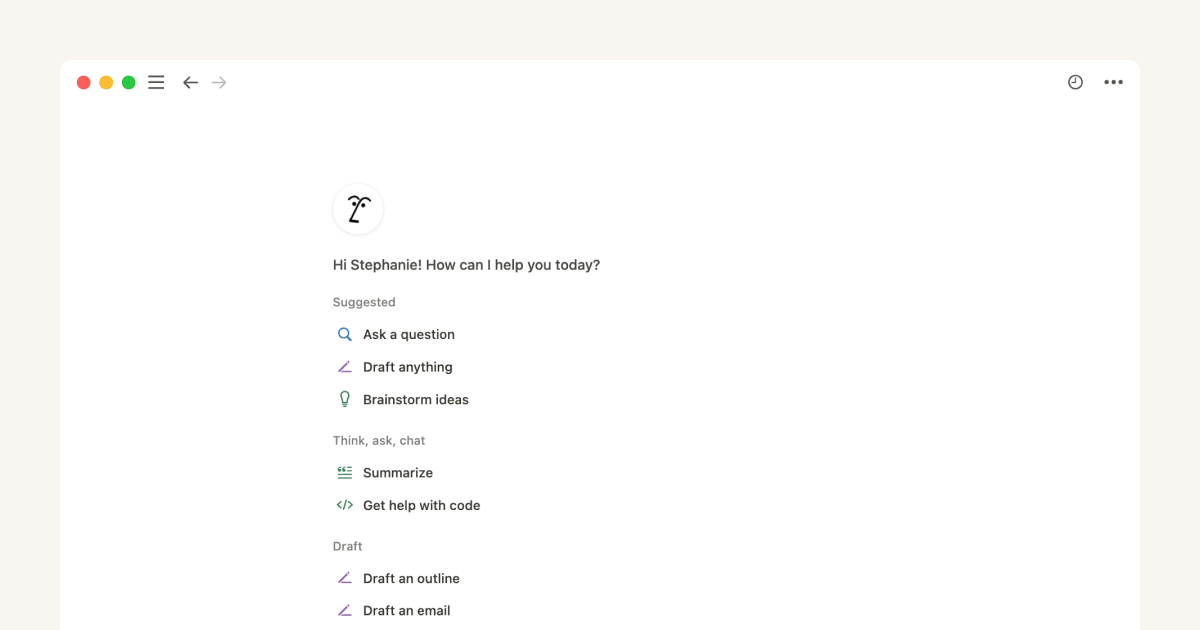近年、AIによるリライトツールが記事コンテンツの更新やブラッシュアップに使われるようになってきました。
「無料で使えるものはあるのか」「どんなツールが実務で使いやすいのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ブログ・コラム記事のリライトに向いているおすすめツールを紹介しました。選び方もわかりやすく解説していますので、参考にしてみてください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
AIリライトツールおすすめ7選
Webコンテンツの改善に適したAIリライトツールを厳選しました。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| ChatGPT | チャット形式で指示。ファイルアップロード対応(有料)。 |
| Notion AI | 文章選択→右クリックでリライト指示。文体や長さの変更も可能。 |
| Copy.ai | テンプレート型でトーン調整が得意。月2,000ワードまで無料。 |
| Catchy | 国産ツール。短文リライト向き。5案を一括出力できる。 |
| QuillBot | 英語中心だが日本語も対応。文法チェック機能付き。 |
| Rytr | 言い換え機能あり。トーン20種以上から選択。月1万文字まで無料。 |
| ELYZA LLM(デモ版) | 日本語に特化した高精度モデル。チャット形式で自然なリライトが可能。 |
ここからは、それぞれの特徴を詳しく紹介していきます。
ChatGPT

ChatGPTは記事の下書きに利用している方も多いと思いますが、リライトにも応用できます。
特に有料プラン( Plus / Team / Enterprise)を利用している場合、ドキュメントファイルをアップロードして指示を出すことが可能です。
下書きをまとめている方にとっては、作業効率を格段に高められる手段といえるでしょう。
たとえば「この文章を丁寧な口調に整えて」「SEOキーワード『○○』を自然に盛り込みながら、読みやすく再構成してほしい」といった形で指示を出すと、的確な修正が返ってきます。
以下の記事ではChatGPTで文章を書かせる際の指示文(プロンプト)を紹介しています。あわせてご覧ください。
Notion AI
Notion AIはドキュメント作成ツール「Notion」に搭載されたAI機能で、リライト作業にも活用可能です。

「AIに依頼」ボタンをクリックするだけで、トーンや長さ、文体の変更などを簡単に指示できる点が特徴です。
Notion上でリライトしたいテキスト部分をマウスで範囲選択します。
右クリックまたはメニューから「AIに依頼」「リライト」機能を選択します。
「もっとカジュアルに」「文章をフォーマルに整えて」「文章を長く」などの指示も可能です。
Notion AIが自然な表現に書き換えてくれます。語順の入れ替えや誤字の修正も自動で行われます。
ただし、無料プランでは20回までという使用回数の制限があるため、頻繁に利用する場合は有料プランを検討してください。
Copy.ai
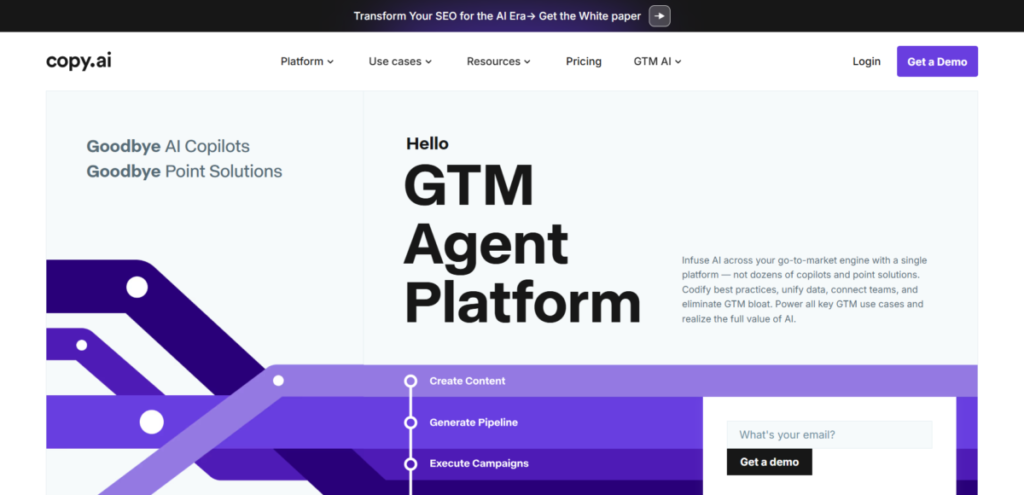
Copy.aiは、英語圏のマーケターが活用している文章生成ツールですが、日本語にも対応しています。
無料プランでは、月に2,000ワード(日本語で約2,500文字程度)という制限があります。
短めの原稿や試し使いには問題ありませんが、定期的にリライト作業を行う場合は有料プランを検討しましょう。
Proプラン(月額約36〜49ドル)ではワード数の上限がなく、長文記事や大量のコンテンツに対しても効率的にリライトを行えます。
Catchy

Catchy(キャッチー)は日本国内で開発されたAIライティングツールで、日本語の自然さと扱いやすさに定評があります。
リライト機能としては「文章をリライトVer.2」が用意されており、最大500文字までの文章に対して一度に5パターンの改善案を提示してくれるのが特長です。
たとえば「もっとやさしい表現に」「専門用語を使わずに」など、具体的な指示が通る点が実務向きといえるでしょう。
無料プランでは月に10クレジットが付与されますが、「文章をリライトVer.2」なら1〜2回程度で使い切ってしまう点に注意が必要です。
QuillBot

QuillBotはリライトと文法チェックを同時に行えるAIツールとして英語圏で高い評価を得ていますが、日本語でも使用できます。
「流暢モード」「クリエイティブモード」などリライト方針を選べるため、用途や文章の目的に応じた表現の調整がしやすいのが特長です。
ただし無料版では約125ワード(日本語でおよそ750文字)までです。
有料プランに切り替えると、より多くの文字数やリライトモードが利用できるようになります。
さらに、Microsoft WordやGoogle Docsとのプラグイン連携にも対応しているため、普段使っている編集環境の中でそのままリライト作業を進められるのも大きな利点です。
まずは無料版で試して、使用感を確かめるのがよいでしょう。
Rytr
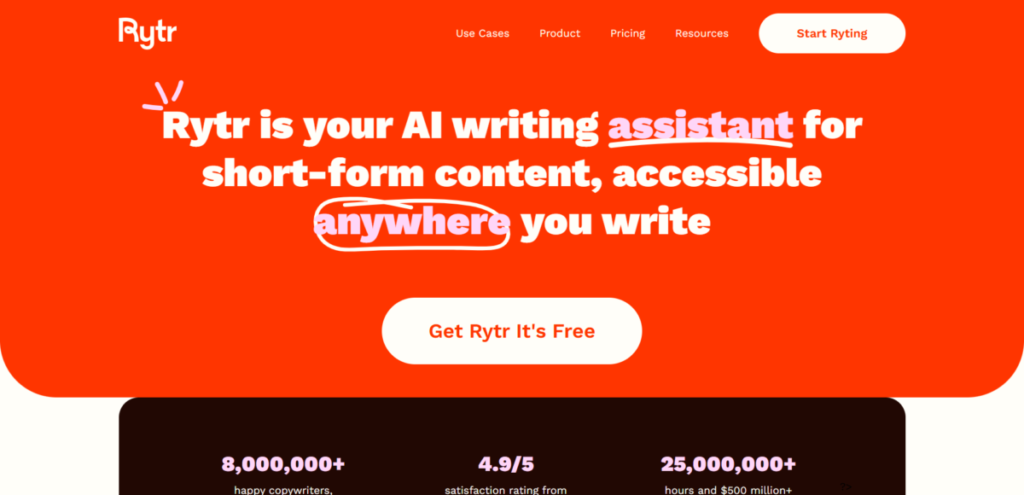
Rytr(ライター)には「言い換え(Rephrase)」機能が用意されており、文章全体のトーンやスタイルは20種類以上から選択できます。
無料プランでは、月に10,000文字まで生成できます。軽めのリライトや試し使いには十分なボリュームでしょう。
有料プランに切り替えると文字数が無制限になり、盗作チェックや複数トーンの切り替えといった機能も使えるようになります。
ただし、日本語対応とはいえベースは英語。少し違和感のある表現が混じることもあります。公開前には、人の目で最終チェックを行ったほうが安心です。
ELYZA LLM (デモ版)

ELYZA LLM(デモ版)は、国産の大規模言語モデル「ELYZA-Shortcut-1.0-Qwen-32B」を採用したAIツールです。
Meta社のLlama 3.1をベースに日本語向けの追加学習が施されており、日本語の文脈理解に強みがあります。
チャット形式で指示を入力するだけで、文章の生成やリライトが行えます。意味の通りや文脈に応じた書き換えにも対応しており、自然で読みやすい文章に整えられる点がメリットです。
Web上でログイン不要のデモ版が提供されていて、文章と指示を送信するだけでリライト結果がすぐに表示されます。まずは気軽に試して、どの程度の品質かを確認してみるとよいでしょう。
AIリライトツールの選び方
ここでは、AIリライトツールを導入する際にチェックしておきたいポイントを紹介します。
- 利用規模・予算に合っているか
- 日本語の精度は高いか
- 文体を指定できるか
- 既存ツールと連携できるか
- SEO対策はできるか
利用規模・予算に合っているか
AIリライトツールを使えば、これまで数時間かけていた修正作業も数分で完了します。外部への依頼コストを抑えたり、少人数でも多くの原稿に対応できるようになったりと、業務の効率化につながります。
サブスクリプション型のツールなら、定額で使い放題です。ただし、月額料金はサービスによって異なり、文字数や使用回数に上限があることも。
一見安いように思えても、1日に何本も記事を扱いたい場合は追加課金が必要になるかもしれません。「どれくらいの頻度で使うか」「トータルでいくらになるのか」といった視点から選ぶようにしましょう。
日本語の精度は高いか
AIリライトツールを選ぶ際は、日本語の自然さにも注目してください。たとえば、語順が不自然だったり、敬語がぎこちなかったりすると、読み手に違和感を与えてしまいます。
海外製でも日本語に対応しているツールもありますが、精度にばらつきがあります。特に直訳調になりやすく、文のつながりが不自然になることも少なくありません。
より自然な仕上がりを求めている場合は国産ツールを選定したほうがよいでしょう。
文体を指定できるか
読みやすく伝わる文章をつくるには、誰にどう届けるかを意識した文体の調整が欠かせません。
ツールによっては、「フォーマル」「カジュアル」「説得力のある」「やさしい」など、トーン(スタイル)を指定できる機能が用意されています。
記事の目的や読者層に合わせて表現を変えられるのであれば、人の手による修正を減らすことができます。
既存ツールと連携できるか
AIリライトツールは、基本的に「サービス(Webサイト)画面にコピー&ペーストする」手順が必要です。作業自体は難しくありませんが、何度もやっていると面倒に感じるかもしれません。
一部のツールでは、ブラウザ拡張やプラグインを通じて、GoogleドキュメントやMicrosoft Wordからそのままリライトを実行できます。
普段使っているツールと連携できるかどうかも確認しておくとよいでしょう。
SEO対策はできるか
AIリライトツールの中には、SEOを意識した機能を備えているものもあります。
たとえば、指定したキーワードを自然に含めたり、競合の上位記事をもとに内容を補強したりといった使い方が可能です。トレンドや検索ボリュームを踏まえて文章を整えれば、検索順位の改善を狙えるでしょう。
ただし、AIは検索意図や読者のニーズを完全に理解できるわけではありません。出力された文章が一見整っていても、内容が薄くなったり、似たような表現に偏ったりすることもあります。
本当に読まれる記事に仕上げるために、独自の切り口や実体験などオリジナリティを加えることを意識しましょう。
まとめ
AIリライトツールは、記事の修正や更新を効率化するうえでとても便利です。ただし、ツールによって機能や使い勝手に違いがあるため、使いこなすには自社に合ったものを選ぶことが大切です。
- 利用規模・予算に合っているか
- 日本語の精度は高いか
- 文体を指定できるか
- 既存ツールと連携できるか
- SEO対策はできるか
AIと人、それぞれの強みを組み合わせながら、自社らしい情報発信につなげていきましょう。
リンキープスでは、AIで作った原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに整えるサービスを提供しています。
プロンプトテンプレートやGA4レポートもついて、毎月の発信がラクに・質高く続けられますので、ぜひご検討ください。