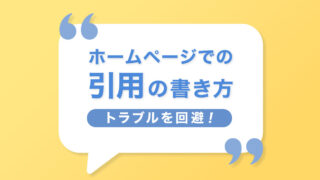生成AIを使って記事を書く際に気になるのが、著作権や景品表示法など法的リスクです。万が一違反が明らかになれば、ブランドの信用や取引先との関係に大きな影響を及ぼすでしょう。
そのため、AIを活用する前に、社内ルール(=編集ガイドライン)をまとめておくことをおすすめします。
本記事では、AI利用で特に注意すべき法律と、編集ガイドラインの雛形を紹介します。トラブルを回避するために、ぜひ参考にしてください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
AI記事で特に注意すべき法律
コンテンツ制作では、著作権法や景品表示法などの法律が深く関わります。ここでは、AIを記事に活用する際、特に意識したい法律を紹介します。
著作権法
著作権法は、「著作物」を創作する著作者の権利を守る法律です。他人が作成したコンテンツ(文章や画像、動画など)を、許可なく自サイトに掲載してはいけません。
引用する場合は許諾がなくとも構いませんが、出典や改変箇所を明示する必要があります。
また、AIが生成した文章や画像は、条件を満たせば著作物として保護されます。ただし、著作物性を認められるには人間による創作的関与(プロンプト設計や編集作業)が必要です。
文化庁はAIと著作権についてというページを用意しています。一度読んでおくことをおすすめします。
景品表示法
景品表示法(景表法)は、消費者を誤認させる表示を禁止する法律です。景表法といえば、くじ引きの景品に関するルールが有名ですが、販促で覚えておきたいのが「ナンバーワン(No.1)表記」です。
実は、「売上ナンバーワン」「顧客満足ナンバーワン」といった表現は、根拠がなければ使用できません。
- 日本一
- 唯一
- 最安値
- 最高
- 最適
以上のような語句がAIが生成した文章の中に含まれていたら、客観的な裏付けがあるかを確認しましょう。詳しくは事例でわかる 景品表示法 (消費者庁)をご覧ください。
ステルスマーケティング規制
2023年10月1日以降、広告やPRであることを明示しない「ステルスマーケティング」は規制対象となりました(ステマ規制)。
特にレビュー記事やタイアップ記事では、冒頭や目立つ位置に「広告」「PR」といった表示を行い、読者が宣伝目的であると理解できる状態にする必要があります。
AI生成コンテンツでは宣伝意図が省かれる場合があり、意図せず違反してしまうかもしれません。
詳細はステルスマーケティングに関するQ&A (消費者庁)をご確認ください。
AI新法
「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)が2025年6月4日に施行されました。簡単にまとめると、AIの適正利用と透明性確保を目的としています。
- 生成物の出所や作成過程を記録する(記録管理義務)
- 誤情報や権利侵害が発生した場合の対応を決める
今回は2025年8月時点の情報をもとに執筆していますが、今後改訂される可能性があります。最新情報はAI戦略 – 科学技術・イノベーション (内閣府)にてご確認ください。
AI編集ガイドラインの雛形
AI編集ガイドラインは、生成AIを活用して記事を作成する際のルールです。
著作権や広告表示などの法律面に加え、読みやすさや表記統一の観点も整理しました。自社のレギュレーションに合わせて加筆修正し、ご活用ください。
- 著作物を複製していないか
- 引用・出典を表記しているか
- 肖像権を侵害していないか
- 嘘の情報が含まれていないか
- ナンバーワン表記を削除したか
- 「広告」「PR」を明記したか
- 個人情報が含まれていないか
- AIサービスの商用利用は可能か
- AI利用時の記録を残したか
- 名称は省略していないか
- 文章は論理的か
- 指示詞を言い換えたか
- 箇条書きに変更したか
- 不適切な表現が含まれていないか
- トラブルが起こった際にどうするか
著作物を複製していないか
AIが生成した文章や画像などの成果物は、既存の著作物に依拠していないか、また類似していないかを必ず確認します。
例えば、画像生成AIで作成したイラストが既存の漫画キャラクターや写真に酷似している場合、著作権侵害を問われる可能性があります。
既存著作物に依拠していると判断される場合には、著作権者からの許諾を取得しなければなりません。
引用・出典を表記しているか
AIが生成した文章に他者のコンテンツを引用する場合は、本文との主従関係を明確にし、必要最小限の範囲で行うことが基本です。
引用箇所には出典元を必ず明記し、改変や編集を加えた場合には、その旨を読者に分かる形で示してください。
以下の記事では、著作権者が定めた利用条件を紹介しています。あわせてご覧ください。
肖像権を侵害していないか
アイキャッチや図解もAIで生成する場合は、実在の人物や場所に過度に似ていないかを確認します。
人物に酷似すると肖像権やパブリシティ権を侵害するおそれがあり、地名や建築物に似すぎると商標権や著作権の問題を招きかねません。
さらに、公序良俗に反する表現や差別的な描写が含まれるリスクもあるため、公開前の点検体制を設けることが望ましいです。
嘘の情報が含まれていないか
AIが生成した文章や画像には、事実と異なる内容や存在しない情報が含まれる場合があります。そのため、公開前には一次情報をチェックすることが欠かせません。
統計であれば総務省や厚生労働省などの公的機関、業界情報であれば公式団体の発表を確認し、裏付けを取ることが望ましいです。
以下の記事ではファクトチェックの方法を紹介しています。あわせてご参照ください。
ナンバーワン表記を削除したか
「ナンバーワン」「最適」といった表記は、裏付けとなる根拠データがなければ使用できません。
例えば「顧客満足度ナンバーワン」と記載する場合は、第三者機関が実施した調査結果や公式統計を示し、出典を明記する必要があります。
AIが生成した文章に誇張表現が含まれていないか、公開前に必ず確認しましょう。根拠が示せない場合は削除または別の表現に置き換えるようにします。
以下の記事では、景表法を含むサイト関連の法律をまとめています。念のためチェックしてみてはいかがでしょうか。
「広告」「PR」を明記したか
広告やPRを目的とした記事や投稿では、読者が宣伝であることを容易に判別できるよう「広告」「PR」などの明示が義務化されています。
AIで生成した文章では宣伝意図が省略される場合があるため、公開前に必ず確認しましょう。レビュー記事やタイアップ記事においても、冒頭や目立つ位置に表示を加えます。
ガイドラインに表示例や注意点を記載しておけば、誰が担当しても同じ基準で運用でき、透明性を担保すると同時に法的リスクを回避できるでしょう。
以下の記事ではステマ規制の文言例を紹介しています。あわせてご覧ください。
個人情報が含まれていないか
記事に特定の人物を識別できる情報が残っていれば、法令違反や信用失墜につながるおそれがあります。(個人情報保護法)
公開前に、氏名・住所・顔写真など個人を特定できる情報が含まれていないかを必ず確認しましょう。
特にインタビュー記事やレビュー記事をAIで補強する場合、元データに含まれる固有名や連絡先がそのまま生成物に出てしまうケースがあるため注意が欠かせません。
AIサービスの商用利用は可能か
生成AIを記事に用いる場合、利用しているサービスの規約を確認することが欠かせません。
一部のサービスでは商用利用が制限されてますし、生成物が運営側に二次利用される可能性が規約に明記されているケースもあります。
さらに、出力内容の管理や保存方法についてもサービスごとに差があるため、事前に把握しておきましょう。
AI利用時の記録を残したか
生成AIを業務に活用する際は、AIに関する情報を残しましょう。記録しておけば、社内外から「AIが作成したものか」と問われたときにも出所を明確に説明できます。
- 利用したサービス名
- バージョン
- 生成日
- プロンプトの内容
- 修正履歴
保存方法は、GoogleドライブやNotionなどナレッジ管理ツールを用いるとよいでしょう。
以下の記事ではChatGPTとNotionをChrome拡張で連携する方法(無料)を紹介しています。ぜひ活用してみてください。
名称は省略していないか
会社名や団体名などは、略さず正式名称で記載することが基本です。
- 会社名
- 団体名
- 資格名
- 学校名
- 商品名
- 地名
- 人名
最初の箇所で「株式会社〇〇(以下、〇〇)」のように表記すれば、その後は略称を使用しても構いません。
商品名や造語には商標権が絡む場合があり、誤記や無断使用によってトラブルが生じる可能性があります。そのため、公式サイトや特許情報プラットフォームでの確認をおすすめします。
文章は論理的か
AIが生成した文章は、一見自然に見えても論理の飛躍や不適切な接続詞が含まれることがあります。そのまま公開すると、読者に意図が伝わらず混乱を招くかもしれません。
段落ごとに接続詞が正しく使われているか、論点が飛んでいないかを点検しましょう。
また、記事全体を通して「課題の提示→解決方法の提示→自社サービスへの誘導」といった流れが成立しているかを確認してください。
指示詞を言い換えたか
AIが生成した文章には、「これ」「それ」「あれ」などの指示詞(指示代名詞)がよく見られます。読者が指し示す内容を正確に理解できず、誤解や読みづらさにつながります。
編集段階では、指示詞をできる限り具体的な名詞に置き換えます。
| 指示詞の例 | 書き換え例 |
|---|---|
| これにより | 上記の対応によって |
| そのような場合 | 誤情報が発覚した場合 |
| このことから | 法改正の結果から |
| それに加えて | ファクトチェックの工程に加えて |
| あれは問題だ | 引用元の不明確さは問題だ |
箇条書きに変更したか
生成AIは、基本的に文章のみを生成します。そのため、複数の項目を紹介する際には、リスト形式や表に書き換えて整理しましょう。
目安としては、三つ以上説明する場合、段落で書くよりも箇条書きにまとめた方が理解が早まります。
また、長い説明が続くときには小見出し(h3タグなど)を追加し、内容を区切ることで記事全体の可読性が高まります。
不適切な表現が含まれていないか
記事においては、誹謗中傷や差別的な表現を用いないことが大前提です。特定の企業や人物を不当に非難すると、法的リスクだけでなく企業の信用低下にも直結します。
以下の記事ではAI記事が炎上した事例や対策方法をご紹介しています。一度目を通しておくことをおすすめします。
さらに、過度にくだけた口語表現や絵文字を使うと、公式な情報発信としての信頼性を損なう場合があります。
例えば、「笑」「!!」といった軽い表現は不適切と定め、代替の語尾や敬体表現を示しておくと担当者が迷わずに済みます。
トラブルが起こった際にどうするか
生成AIを使った記事で権利侵害や誤情報を指摘されたときは、すぐに対応できる流れを決めておくことが欠かせません。
まずは問題の記事を一時的に非公開にし、社内で内容を確認したうえで修正版を公開する手順を用意しましょう。その際、誰が責任を持つのか、対応の期限はいつまでかを決めておくと混乱を避けられます。
また、緊急連絡先として社内の担当者リストだけでなく、顧問弁護士・法務担当など外部の相談先をまとめておきます。
まとめ
生成AIは記事執筆を効率化できますが、著作権や広告表示などの法務リスクも抱えています。
法律を遵守しながら、品質も安定させるにはガイドラインが欠かせません。今回紹介した雛形を基に、自社の業務や体制に合わせてルールを整備してはいかがでしょうか。
リンキープスは、AIで作った原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに整えるサービスを提供しています。
プロンプトテンプレートやGA4レポートもついて、毎月の発信がラクに・質高く続けられます。AIが生成した文章から集客できていない方は、ぜひ一度「AI編集さん」の詳細をご覧ください。