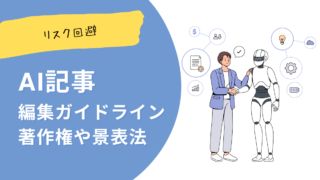生成AIの活用が広がるなか、「本当に効果があるのか」「自社でも使いこなせるのか」と不安を感じる中小企業の方も多いのではないでしょうか。
気になってはいるけれど、コストやリスクを考えると一歩踏み出せない―そんな声も少なくありません。
そこで今回は、生成AIを導入する前に知っておきたい課題と対処法をわかりやすく解説します。導入を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
生成AIの課題
生成AIは、業務の効率化や情報発信の強化に役立つツールとして注目されていますが、導入にあたっては慎重な検討が欠かせません。
- 費用対効果が不透明
- 社内で定着しない
- 専門知識の不足
- ハルシネーション(嘘)
- 機密情報の取り扱い
- 著作権の侵害
- 出力の偏り(差別)
まずは、生成AI特有の課題を一つひとつ紹介していきます。
費用対効果が不透明
生成AIには無料プランも存在しますが、業務で本格的に活用する場合は、ライセンスの取得や専用ツールの導入、社内教育などでコストが発生します。
にもかかわらず、「どれほど業務が効率化するのか」「売上にどう影響するのか」といった具体的な効果は導入前には見えにくいのが現実です。
実際に、導入企業の約4割が「効果を実感できていない」との調査結果もあります。特に限られた予算で経営を行う中小企業にとって大きなハードルとなるでしょう。
社内で定着しない
生成AIを導入しても、実際の業務に活かされず形だけで終わってしまうケースは少なくありません。原因として「使い方がわからない」「目的が明確でない」「操作が煩雑」が挙げられます。
特に中小企業では、専任のIT担当者が不在だったり、教育に割けるリソースが限られていたりすることが多く、導入後のフォローが十分に行われない傾向があります。
その結果、「誰も使わないツール」として放置されてしまい、コストだけがかかってしまうのです。
専門知識の不足
生成AIを活用するには、AIツールの操作方法だけでなく、データの扱いや情報セキュリティリスクに関する知識も求められます。
しかし、多くの中小企業では、AIやデータに詳しい人材が社内におらず、必要なスキルが不足しているのが実情です。
また、生成AIの進化は早く、ツールの仕様やルールも頻繁に変わるため、導入後も継続的に知識をアップデートする体制が必要になります。
十分に把握しないまま使い始めてしまうと、うまく活用できないだけでなく、誤った運用によってトラブルを招くリスクも高まります。
ハルシネーション(嘘)
生成AIは、人間のように自然な文章を作成できますが、ときに事実と異なる情報をもっともらしく提示してしまうことがあります。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象です。
AIは確率的に最適な語句を並べて文章を生成しているため、根拠のない内容でも一貫性のある表現になってしまうのです。
特に、記事制作やWebでの情報発信に使う場合、誤情報をそのまま公開すると、読者との信頼関係を損ねたり、企業の信用を傷つけたりするリスクも考えられます。
以下の記事ではAI記事が炎上した事例を紹介しています。具体的にどのようなリスクがあるのか、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
機密情報の取り扱い
生成AIは、入力したテキストをクラウド上で処理する仕組みが一般的です。そのため、社内の機密情報や顧客データを入力した場合、外部に送信・保存されるリスクが伴います。
たとえば、契約書の内容や未発表の製品情報などを不用意に扱うと、情報漏洩やセキュリティ事故につながる可能性も。さらに、一部のAIサービスでは、入力内容がAIの学習データとして使用されることが利用規約に明記されています。
著作権の侵害
生成AIは、インターネット上に存在する大量のテキストや画像をもとに学習しています。その中には著作権が存在するコンテンツも含まれており、AIが生成した文章や画像に、既存の著作物と酷似した表現が含まれるかもしれません。
たとえ意図的でなくても、著作権を侵害してしまえば、法的なトラブルに発展するおそれがあります。特に企業のWebサイトや広報資料に使う場合、無断使用が明るみに出ると信用を大きく損なうことにもなりかねません。
出力の偏り(差別)
生成AIは既存データをもとに学習しているため、元のデータに偏りや差別的な表現が含まれていた場合、それが出力にも反映されることがあります。
たとえば、性別や国籍、職業に対する固定観念を助長するような表現が出てくるケースも存在するのです。
悪意はなくとも、社会的な配慮に欠ける内容として問題視されれば、企業のイメージに悪影響を及ぼしかねません。
生成AIの課題に対処する方法
生成AIには多くの可能性がある一方で、導入や活用にはさまざまな懸念もつきまといます。だからこそ、リスクを正しく理解し、事前に対処法を知っておくことが重要です。
ここからは、よくある課題に対する解決策を紹介します。
段階的な導入
生成AIを導入する際は、いきなり全社的に展開するのではなく、まずは一部の業務や部署で試験的に使ってみるのが効果的です。これを「PoC(Proof of Concept/概念実証)」と呼びます。
たとえば、社内文書の作成や簡単な記事構成案の生成など小さな業務からスタートし、実際にどれだけ業務が効率化されるのかを検証します。
その結果をもとに、本格導入の可否や必要な改善点を判断できるため、無駄なコストや混乱を避けやすくなります。段階的に進めることで、社内の理解や活用スキルも自然と育ちやすくなるでしょう。
以下の記事ではChatGPTに文章を書いてもらうための指示文(プロンプト)を紹介しています。あわせてご覧ください。
AI倫理方針の設定
生成AIを安全かつ効果的に活用するには、企業としての利用ルールや基本方針をあらかじめ定めておくことが重要です。
たとえば、「どんな目的で使うか」「どういった使い方を避けるか」といった基準が曖昧なままだと、現場ごとに判断がばらつき、不適切な使い方やトラブルを招く可能性があります。
まずは簡単なマニュアルでも構いませんので、社内で共有しやすい形で方針を明文化しましょう。
以下の記事では編集ガイドラインのテンプレートを紹介しています。AIを活用する前に、ぜひ一度ご覧ください。
法律・ガイドラインの遵守
生成AIを業務で活用する際は、関連する法律の確認が欠かせません。たとえば、個人情報を扱う場合には「個人情報保護法」、著作物を利用する場合には「著作権法」への理解が必要です。
違反すると罰則を受けるだけでなく、企業の信頼性にも深刻な影響を与えかねません。
経済産業省が公開しているガイドラインには、出力管理や利用者責任のあり方などが整理されています。導入前に資料を確認することをおすすめします。
判断フローや承認プロセスを設定する
生成AIの出力には、事実誤認や不適切な表現が含まれることがあります。そのため、生成結果をそのまま使用せず、確認や承認のプロセスを事前に整えておきましょう。
たとえば、一次チェックを担当者が行い、その後に上長や別部門で最終確認を実施するといった多段階の手順が有効です。
また、重要な出力には根拠の提示をAIに求めたり、ログを記録しておいたりすることで、責任の所在を明確にできます。
以下の記事ではファクトチェック(事実確認)の方法を紹介していますので、あわせてご覧ください。
社外リソースの活用
社内に十分なノウハウがない状態で生成AIを導入しようとすると、思わぬ混乱や誤った使い方につながるおそれがあります。そこで有効なのが、外部の専門家やITベンダーの支援を受けることです。
導入計画の設計から活用シナリオの立案、セキュリティ面のアドバイスまで、必要な場面に応じて柔軟なサポートを得られます。また、外部講師による研修や勉強会を通じて、社内の理解を深めることも可能です。
最初は社外の知見を取り入れながら、最終的には自社で安定的に運用できる体制づくりを目指しましょう。
リンキープスでは、AIで作った原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに整える月額制サービスを提供しています。AIを記事制作に活用する予定の方は、ぜひ「AI編集さん」をご検討ください。
まとめ
生成AIは、文章作成や情報整理などを効率化できる便利なツールです。うまく使えば、業務の時間短縮やWebでの発信力アップが期待できます。
ただし、「効果がはっきりしない」「使いこなせないのでは」といった不安が、導入をためらう原因になっています。
だからこそ、リスクを理解したうえで、小規模な導入から始めたり、社内ルールや確認体制を整えたりすることが大切です。外部の力も活用しながら、社内の理解と仕組みづくりを進めていきましょう。
「AIで記事の下書きを作りたい。でも、どうやって指示すればよいのだろう」と困っている方は、AI編集さんにご相談ください。
プロンプトテンプレートやGA4レポートもついて、毎月の発信がラクに・質高く続けられます。詳細は以下のページにてご覧ください。