「ホームページで引用したいけれど、トラブルは起こしたくない…」と困っていませんか。
引用のルールをしっかり守れば著作権侵害にはあたらず、記事の信頼性も高められます。
そこで今回は現役ライターが引用の書き方を紹介します。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
引用方法の種類
実は引用方法には「直接引用」と「間接引用」の2種類があります。
ホームページで引用する際は、基本的には間接引用ではなく直接引用を使うことをおすすめします。
まずは引用方法の違いについて確認しましょう。
直接引用
「直接引用」の条件は2つあります。
- 何も手を加えずそのままホームページに載せる
- 出典は一次情報(オリジナルのデータや文献)
引用しておきながら情報源を示さないと盗用、著作権侵害となってしまいます。
間接引用
「間接引用」は引用したい情報を、要約したり表現を変えたりして自分で書き直すことです。
引用したい部分が長すぎる場合には「著者は〇〇と指摘しています」と、まとめた方が分かりやすいケースもありますよね。
- 著書は〇〇と指摘しています。
- 著者によると、〇〇とのことです。
- データによると、〇〇という可能性があります。
つまり、自分の言葉で他人の意見を伝えたいときに間接引用を使います。間接引用では、意味や解釈が変わらないように細心の注意が必要です。
なお、一次情報から引用された情報を、さらに引用することを「孫引き」と言います。
孫引きは意味や解釈を間違えていたり、勝手に文章を変えていたりする危険性があるので、トラブルの原因になりやすいです。
直接引用のルール
著作者の許可なく、ただ転載するだけでは著作権侵害になってしまいます。著作権法第32条(引用)を確認してみましょう。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用 著作権法 | e-Gov法令検索
ここからは、著作権を侵害しない直接引用のルールを分かりやすく紹介します。
公表されている情報を引用する
公表されている情報、かつ引用のルールを守っていれば、著作者本人の許諾は必要ありません。
ここで言う「公表」とは、不特定多数が見ることができる状態のものです。
- ホームページ(誰でもアクセスできるページ)
- 資料
- 書籍
- 報告書
- 論文
例えばホームページはネットにアップロードした時点で誰でも閲覧できるので、公表されている情報に当てはまります。
しかし、非公開ページ・会員限定ページなど閲覧できる人が限定されているページは公表されている情報に当てはまりません。
- ホームページ(誰でもアクセスできる)
- ブログ記事(誰でもアクセスできる)
- 非公開ページ
- 会員限定ページ
内容は変更しない
引用では、一語一句変えてはいけません。
引用元の文章に誤字脱字があった場合でも書き直しません。もし書き直してしまったら、それは引用ではなくコピペ記事になってしまいます。
引用を載せる必要性がある
引用は、記事の根拠を示したり補足説明をしたりするものです。そのため引用部分がメインになったり、必要ない部分に引用を使ったりできません。
「なぜ、この引用を載せる必要があったのか」を明確に説明できるところのみ使うようにしましょう。
- 引用部分がメインとなっている
- 関係ないのに引用する
引用部分が分かるようにする
引用部分が明確に分かるように「引用符」を使いましょう。
引用符は特に決まりはありませんが、Webサイトでは「“”(ダブルクォーテーションマーク)」がよく使われています。
引用部分が短い場合「」や『』でも構いません。
WordPressには引用ブロックが用意されているはずなので、それを使いましょう。
引用ブロック
引用元
情報源を書く
引用したら情報源を明記する必要があります。引用した媒体によって情報の記載方法が異なるので、それぞれ解説していきます。
書籍
書籍を引用する場合、下記の項目を記載します。
- 著者名
- タイトル
- 発行年
- ページ数(例:P10-11)
読者が引用元の書籍を読んだ時に、すぐに引用部分に辿り着けるようにすることが大切です。
Webサイト
Webサイトを引用する場合は、サイト名・ページ名・URLを記載します。
- サイト名
- 該当ページのタイトル
- リンクURL
よく更新される情報は、引用した日付も記載しておくと良いです。
データ
公表されているデータや資料を引用する場合は調査結果の数字のみ引用できます。
- データ名
- 作成者名
- 入手先URLや資料名
- ページ数(一部を引用する場合)
掲載されている図表は許可なく引用できないため、自分で改めて図表を作る必要があります。
SNS
TwitterやInstagramなどSNSを引用する場合は「埋め込み」を利用します。
スクリーンショット掲載やテキストのコピペはトラブルの元になるため、ご注意ください。
SNSによって引用方法は異なるため、例としてTwitterの手順(PC)を説明します。
- 引用したいつぶやきをクリック
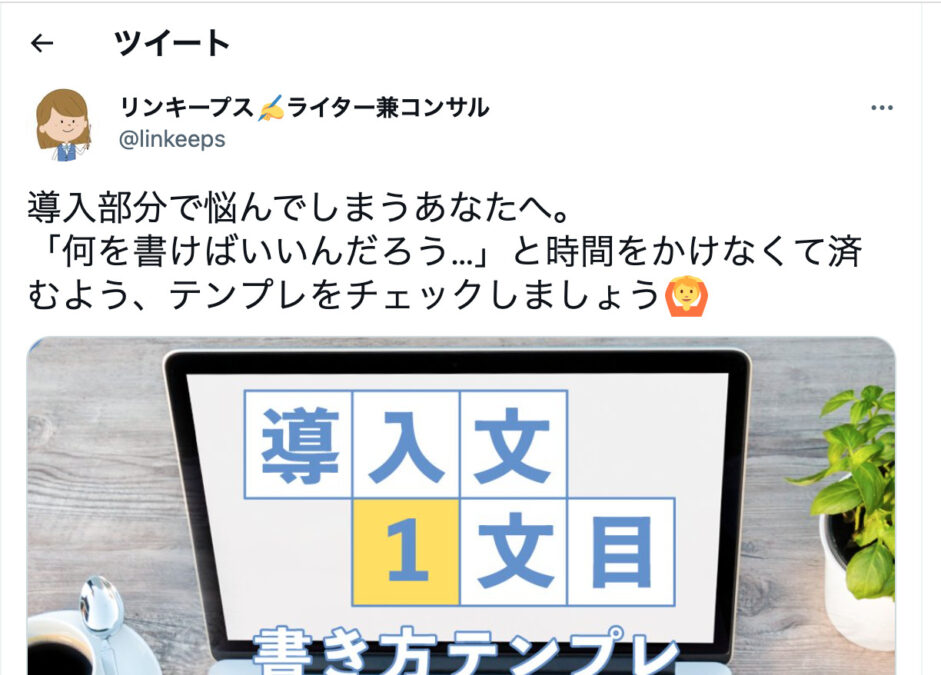
- 「…」をクリックする
- 「ツイートを埋め込む」をクリックする

- 「Copy Code」をクリックする(コピー)
- WordPressに貼り付ける
「カスタムHTML」ブロックに貼り付ける
まとめ
今回はホームページでの引用の書き方を紹介しました。直接引用の場合、以下のルールを守れば著作権侵害にはなりません。
- 公表されている情報を引用する
- 内容は変更しない
- 引用を載せる必要性がある
- 引用部分が分かるようにする
- 情報源を書く
トラブルを回避するために、引用方法をしっかりチェックしましょう。

