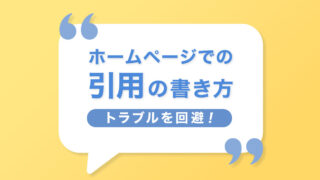近年、生成AIを活用して記事を書く企業が増えてきました。しかし、誤情報の拡散や著作権侵害、ブランド価値の低下といった深刻なトラブルが起きるケースも少なくありません。
そこで今回は、実際に起きた失敗事例や炎上の原因を整理し、Google評価の最新基準とあわせて対策方法を紹介します。安全で効果的にAI記事を活用するために、ぜひ最後までご覧ください。

リンキープス ライター兼コンサル
これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。
「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。
集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!
記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。
なぜ炎上する?AI記事ならではの特徴
生成AIによる記事制作は作業効率を大幅に高めますが、その特性ゆえに誤情報や不適切な内容が含まれる危険性があります。
まずは、生成AIがトラブルを引き起こす背景を確認しましょう。
- 誤情報を生みやすい構造
- 権利侵害のリスク
- 社会的・文化的配慮の欠如
- 独自性や深みの不足
誤情報を生みやすい構造
生成AIは、大量のデータをもとに文章を構築しますが、情報の正確性を判断する機能は備えていません。
そのため、事実とは異なる内容をもっともらしく提示する「ハルシネーション」が起こりやすいというデメリットが存在します。
偽の情報は読者に誤解を与えるだけでなく、公開後にSNSやメディアで急速に拡散されるケースも少なくありません。
権利侵害のリスク
生成AIは、学習時に取り込んだ既存の文章や画像をもとに新しいコンテンツを生成します。
しかし、その過程で元の著作物と類似した表現が出力される場合があり、無断利用とみなされる恐れがあります。記事に掲載する画像やイラストを生成する際も、肖像権や商標権の侵害にもなりかねません。
以下の記事では、サイトを運営する上で知っておきたい「著作権法」「薬機法」などを紹介しています。あわせてご参考ください。
社会的・文化的配慮の欠如
生成AIは、言葉の背後にある文化的背景や社会的文脈を深く理解することができません。そのため、差別と受け取られる表現や、社会的弱者を軽視するように見える記述を含む場合もあります。
また、歴史的・宗教的に重要な出来事や人物を軽んじるような描写が混ざってしまうケースも考えられます。
対象となる文化や地域の人々に精神的な損害を与えるだけでなく、社会からの反発を招く可能性が高くなってしまうでしょう。
独自性や深みの不足
生成AIは過去のパターンをもとに文章を組み立てるため、深い洞察に欠ける傾向があります。
例えば、業界特有の事例や数値を盛り込むべき分析記事が、一般的な説明だけで構成され、読み手に新しい発見を与えられないといったケースが多く見られます。
表面的な説明では読者の関心を引きにくいため、サイト離脱率が悪化し、問い合わせや注文にもつながらないでしょう。
AI記事の炎上事例
2023年以降、AI生成コンテンツの炎上が国内外で相次いでいます。
- 福岡:PR記事で存在しない祭りを掲載
- CNET:41本に重大な誤り、訂正へ
- Microsoft Start:フードバンクを「観光スポット」 と紹介
- Appleニュース:要約に誤り。BBCなどから批判
ここからは、具体的に何がいけなかったのかを紹介します。
福岡:PR記事で存在しない祭り
2024年、福岡市の「福岡つながり応援プロジェクト」が生成AIを活用して作成した観光PR記事が炎上しました。記事内では、存在しない祭りを紹介したほか、他県にある施設を福岡の名所として誤って掲載していました。
SNS上で市民や観光関係者から多数の指摘が寄せられ、誤情報が急速に拡散。最終的に、運営側は全記事の削除とAI記事制作の停止を発表しました。
CNET:41本を訂正へ
米国の大手テックメディアCNETは、AIによって生成した金融関連の記事を人間の監修なしで多数公開していたことが発覚しました。
調査の結果、77本の記事のうち41本に重大な誤りや出典不明の引用が含まれており、盗用とみなされるケースも確認されています。
CNETは訂正と謝罪を余儀なくされ、長年築いてきたブランドの信頼が損なわれました。
Microsoft Start:フードバンクを「観光スポット」
2023年、Microsoftが運営するニュースポータル「Microsoft Start」に掲載されたAI生成の旅行記事が批判を受けました。
カナダ・オタワのフードバンクを、「空腹で行くべき観光スポット」と紹介してしまったのです。フードバンクは生活困窮者を支援する施設であり、この表現は倫理的にも社会的にも不適切とされました。
批判が拡散した結果、該当記事は削除されましたが、AIが文脈や社会的背景を十分に理解できない課題が浮き彫りになりました。
Appleニュース:要約の誤り
2025年、AppleがiPhone向けに提供した「AIニュース要約」機能が複数の主要メディアから強い批判を受けました。
AIが生成した要約は、BBCやニューヨークタイムズなどの元記事の趣旨や取材内容を歪める誤った内容を含み、読者に誤解を与える恐れがあったのです。
特に国際ニュースや社会的に敏感なテーマでは、意図しない誤情報の拡散につながる危険性が指摘されました。BBCをはじめとする報道機関は、機能の改善や撤回を正式に要求し、情報の正確性確保を強く求めました。
GoogleはAI記事をどう評価する?
2025年1月、Googleは検索品質評価ガイドラインを改定し、AI生成コンテンツの評価基準をより厳格化しました。簡単にまとめると、「ほぼすべてがAI生成で、独自性や付加価値がない」記事は最低評価とされます。
検索品質評価者向けガイドラインには、大量生成されたコンテンツの不正使用(セクション 4.6.5)と、ほとんど手間をかけず、ほとんど独自性がなく、ほとんど価値を付加せずに作成されたメイン コンテンツ(セクション 4.6.6)の両方に関する評価方法が記載されています。
ただし、AI活用そのものは禁止されていません。人間の専門的な知見や独自調査を大幅に加えた記事は中〜高評価も可能です。
今後は、下書きやアイデア段階でAIを利用し、最終的には人間の編集・監修を経て、独自性と信頼性を確保することが重要と言えるでしょう。
以下の記事ではGoogleが嫌う「低品質コンテンツ」について詳しく説明しています。あわせてご覧ください。
炎上や低評価を防ぐ!AI記事の注意点
生成AIを記事制作に取り入れること自体は有効ですが、運用方法を誤ると誤情報や権利侵害、ブランド価値の低下を招く恐れがあります。
ここからは、安全かつ効果的にAI記事を活用するためのポイントを紹介します。
- 一次情報を確認する
- 文章や画像の権利をチェックする
- 読む人が不快にならない表現にする
- 歴史・文化を理解する
- 自分の経験や事例を盛り込む
- 公開後も反応を見て早めに対応する
一次情報を確認する
生成AIは過去のデータをもとに文章を組み立てるため、現地取材や最新情報の取得は行えません。その結果、事実と異なる内容や古い情報が紛れ込む「ハルシネーション(幻覚)」が起こりやすくなります。
例えば、観光案内記事で既に終了したイベントを紹介したり、存在しない店舗を掲載したりといったケースが考えられます。
公開前には数字や固有名詞、地名などの情報を確認し、必要に応じて現場取材や専門家への確認を行うよう心がけましょう。
以下の記事では記事監修を依頼する際の相場・流れをまとめています。一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
文章や画像の権利をチェックする
生成AIは学習時に既存の文章や画像を参照しているため、出力内容が元の著作物と似通う場合があります。
特に文章では、引用元が明示されず、原文と類似した表現が含まれると盗用と判断され、法的な問題に発展してしまうかもしれません。
引用や参考情報は出典を記載し、利用条件を満たした形で活用するようにしましょう。
以下の記事では引用する際のルールを紹介しています。念のため、確認することをおすすめします。
読む人が不快にならない表現にする
生成AIは言葉の背後にある文化的・社会的な文脈を十分に理解できないため、意図せず倫理的に不適切な表現を含む場合が見受けられます。
トラブル回避のためには、公開前に編集者や広報担当者が精査を行い、企業理念や社会的価値観と合致しているかを確認することが不可欠です。
歴史・文化を理解する
生成AIは、過去の出来事や人物に関する情報を推測で補ってしまうため、年代や背景を誤って出力するケースも見られます。
特に教育や観光など正しい歴史認識が求められる分野では重大な問題となり、関係者からの抗議や信用の失墜を招く恐れがあります。
AIの出力を信じすぎず、信頼性の高い史料を複数参照し、専門家による事前確認を行うようにしましょう。
自分の経験や事例を盛り込む
生成AIが作成した文章をそのまま公開すると、独自性や専門性が不足し、読者にとっての価値が下がります。さらにGoogleから「薄い内容」と判断され、検索順位の低下や信頼の喪失を招くリスクもあります。
AIを活用する際は、出力結果に独自調査の成果や自身の経験談、専門家の解説などを加えるようにしましょう。手間はかかりますが、オリジナリティと説得力を兼ね備えたコンテンツへと高められます。
公開後も反応を見て早めに対応する
AI生成コンテンツに誤りや不適切な表現が含まれて炎上した場合、初動対応が遅れるほど被害は拡大します。SNSやメディアでは批判が急速に広がり、ブランドイメージの回復が難しくなるためです。
公開後は、GA4を活用してモニタリングしましょう。拡散された場合はアクティブユーザーが爆発的に増加すると考えられるので、「ユーザー数」をチェックしたほうがよいです。
以下の記事では、GA4でアクティブユーザーを確認する方法を紹介しています。あわせてご参考ください。
また、「AI記事に誤情報が含まれていると指摘された場合の対応フロー」を事前に定めておくことも重要です。速やかに謝罪や訂正が行える体制を整えていれば、影響を最小限に抑えられます。
まとめ
AIは短期間で多くのコンテンツを生み出し、企画や発想の幅を広げる有力な手段として注目されています。しかし、誤情報の拡散や著作権侵害、不適切な表現による炎上といったリスクが潜んでいるのも事実です。
加えて、Googleの評価基準が厳格化されたため、独自性や付加価値に欠けるAI記事は検索順位が下がりやすくなりました。
炎上や低評価を防ぐには、事実確認や監修を含む運用ルールを整えることが重要です。ただし、すべてを社内で対応するのは大きな負担となるでしょう。
リンキープスでは、AIで作成した原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに仕上げるサービスを提供しています。AIをうまく使いこなしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。